はじめに
モーツァルトは、短い生涯の中で膨大な数の名作を生み出しました。
その幅広いジャンルと作品の魅力を、いくつか代表的な作品とともにご紹介します。(Kとはモーツァルトの作品番号の表記。「ケッヘル」と読みます)
・オペラ
【魔笛 K.620】
王子が魔法の笛を手に入れてお姫様を救い出す、冒険あり、成長ありのファンタジー作品です。
見どころは『夜の女王のアリア(復讐の炎は地獄のように胸に燃え)』です。高音域を「これでもか」という位に歌いながらどんどん引き上げていく様子に、ソプラノ歌手の超絶技巧を堪能できる爽快感があります。

・教会音楽
【レクイエム ニ短調 K.626】
謎の「黒衣の依頼人」から依頼を受け、その後体調を崩し、自分の死の影に怯えながらも「これは自分自身の葬儀のためのものだ」と呟きながら作曲し、未完のまま亡くなったと言う逸話の残っている曲です。
モーツァルト自身の人生の集大成をかけたような、鬼気迫る迫力があります。
彼の死後、弟子のフランツ・クサーヴァー・ジュースマイヤーにより補筆され、完成となりました。
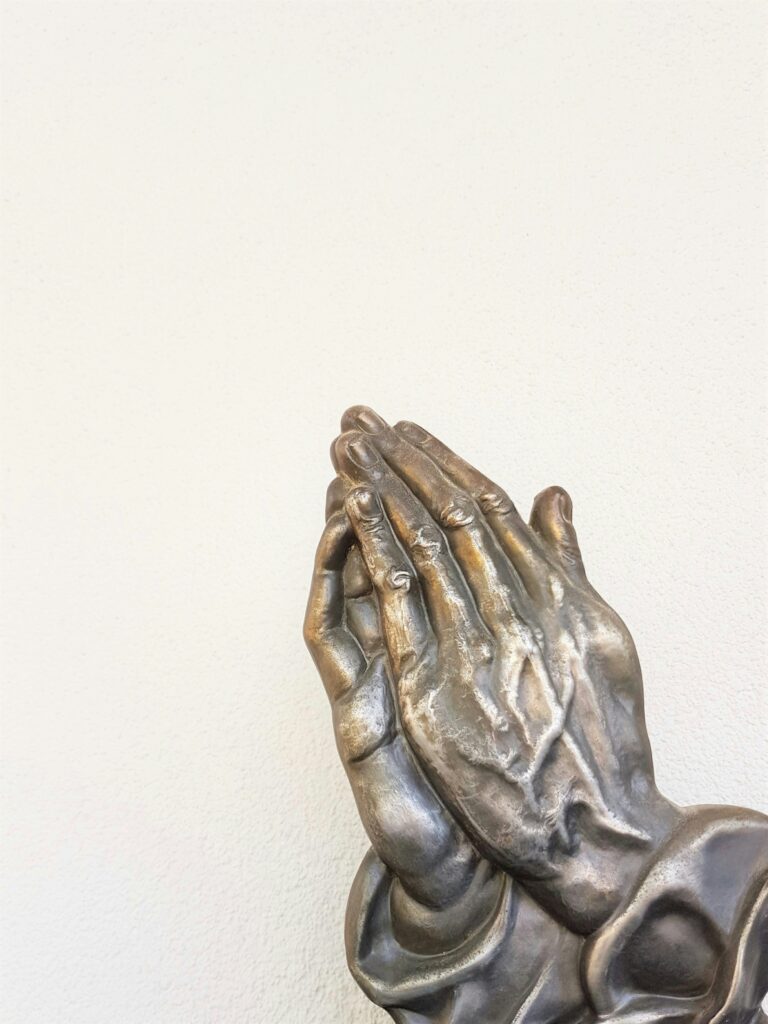
・歌曲
【夕べの想い K.523】
とても優しく柔らかい、語りかけるような温かさを感じる歌曲です。
「自分はいずれ命の幕が閉じるが、墓の前で泣く親しい人に天国の息吹を伝えましょう」という命の終わりを歌う曲ですが、朗らかで、子守唄のような聴き心地です。

・交響曲
【交響曲第40番 ト短調 K.550】
交響曲第39番、第40番、第41番は≪モーツァルトの3大交響曲≫と言われています。
この音楽史にも遺る大傑作を、モーツァルトは1788年6月26日から8月10日までのたったの6週間という短かい期間で、誰からの依頼もない状態で描き上げています。これは、筆が速いでは説明がつかない、音楽史のミステリーとして今でも語られています。

今回はその中から、第40番をご紹介します。
1楽章の冒頭のメロディーは、皆さん1度は耳にしたことがある旋律なのではないでしょうか?
重厚感、悲しさ、祈り、その中に見え隠れする世界を肯定するモーツァルトらしい明るさが感じられ、聴くとエネルギーが充電された気分になります。
・協奏曲
【ピアノ協奏曲第20番 ニ短調 K.466】
重厚感の中にあるモーツァルトの軽やかさ、短調の中にあるモーツァルトの朗らかさが感じられて、様々な感情が揺さぶられる曲です。2楽章の清らかな柔らかさも美しいです。

【オーボエ協奏曲 ハ長調】
あたたかい音質のオーボエという楽器とモーツァルトの朗らかさの組み合わせが、聴き手をとても安らかな気持ちにしてくれます。
朝焼けや山並みがイメージされるような、優しい旋律が魅力です。
室内楽
【セレナード第13番 ト長調 K.525】
「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」の名前でモーツァルトの作品では最も親しまれている作品のひとつです。日本語に訳すと「小さな夜の音楽」。
夜の音楽と言いながら、華やかで明るい曲調が朝の気持のいい1日の始まりにぴったりです。
【クラリネット五重奏曲 イ長調 K.581】
ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバスとクラリネットで編成されており、クラリネットの優しい音色と弦楽器で奏でられるゆったりとした温かみのある美しい旋律に癒されます。

・ピアノ曲
【ピアノソナタ第8番 イ短調 K.310】
モーツァルトの短調の曲がもともと珍しいのですが、それだけではなくピアノソナタで初めて短調で描かれた曲です。
この曲はモーツァルト自身の母が亡くなった直後に描かれ、ただの短調の曲ではなく、モーツァルト自身の悲しみや喪失感も反映されています。
1楽章の切迫したような短調の旋律、2楽章の祈りのような清らかさ、3楽章の疾走感や激情の感じられる趣きは、本来の朗らかなモーツァルトの作品の中では異質であり、心に訴えてくるものがあります。

まとめ
モーツァルトの音楽は、時を越えて今もなお、私たちの心に澄んだ響きを届けてくれます。



コメント