【介護職で感じる「音の洪水」】
HSPであると、職場環境が辛く感じる場面が多くあるかもしれません。
昨今は、会社にも産業カウンセラーがいたり、メンタルヘルスには理解が少しずつ広がっている印象ですが、HSPはまだ、声に出しにくい、配慮をしてほしいと言いにくいボーダーラインかな?という印象があります。
申告すると「だから何?」「大袈裟な」と言われてしまうかも、と日々のしんどさを自分の内面で抑えている人が多いのではないでrしょうか?
私自身の話をさせていただくと、昔から耳が良すぎて聴覚過敏に悩まされています。
そんな私の仕事は介護職。
介護職の現場の普段の音は、まず大音量でテレビがかかっています。しかもリビングに2台。違う番組の時もあります。そこにどこからか演歌や唱歌のCDの音楽が聞こえてきたり。
皆大声で会話をしており、そこにナースコール、電話、職員同士の数組の会話。
もう毎日吐きそうで、仕事が終わるとどっと疲れます。
それでも介護の現場で働き続けなきゃいけない状況で、自分なりの環境への処世術を身につけました。

工夫①:チューニングを意識的に合わせない
気になると人は聞くことに感覚を合わせ、全部の情報を入れてしまいます。
でも、聴覚ではなく視覚の場合、世の中には看板や情報、花や動物、人混みだとたくさんの人の顔など、目に入る情報は溢れているのに、見ようとしなければ疲れないですよね。あの感覚を耳でやるのです。
「聞こえたらぼかす」「頭で音や言葉を確認しない」「なるべく音を受け流す」
これを意識するだけで、うるさいのは変わりないけど、疲労度は格段に楽になります。
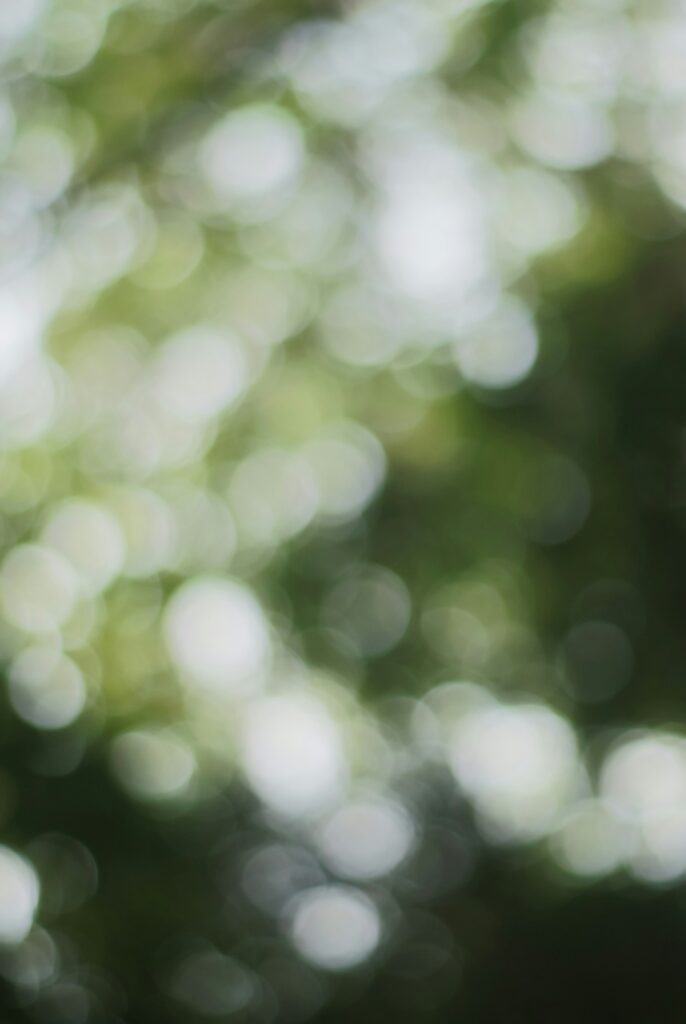
工夫②:視線や人の感情にもチューニングし過ぎない
HSPの人は、人の目線やちょっとした表情の変化やその空間を纏っている空気も敏感に感じ取り、人一倍人間関係に心を消耗する傾向があると思います。
工夫①と同じ方法を人の視線や表情などに応用することで、この消耗を楽にすることが出来ます。
あえて入る情報にチューニングを合わせない。相手の表情、言葉の選び方もその人の問題で、自分事として受け取る必要はありません。
「相手の機嫌=自分の責任」ではありません。失敗は挽回すべきだけど、人の機嫌を取る義務はない、とマインドセットする事も、心を守る大事な工夫です。

工夫③:信頼できる人に伝える
HSPの人は、感覚の鋭敏さと共に、人の感情を察してしまう繊細さを持っているので、「迷惑をかけたくない」と我慢しがちですが、環境を少し変えるだけで働きやすくなります。
愚痴や弱音ではなく、「働きやすくするために」という前向きな姿勢で環境の苦手さを伝えると、周囲も理解してくれることがあります。
リアルな身近な味方の存在は大きな支えになります。

【まとめ】
感覚過敏がありながら働くことは簡単ではありません。
しかし、感覚を守る工夫や境界線を意識することで、少しずつ心が楽になります。
私もまだ試行錯誤の途中ですが、あなたも「無理をしすぎず、自分を守る方法」を探してみてください。
そして、あなたの心の声を大切にしながら働くことを忘れないでください。
あなたはどんな工夫で心を守っていますか?



コメント